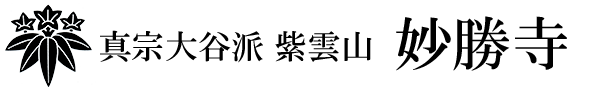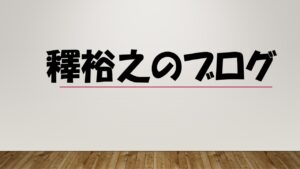8月25日、26日の二日間京都の真宗本廟宗務所におきまして2025年度真宗大谷派夏期教師検定試験が行われ、本寺寺族が受験をしてまいりました。真宗大谷派教師とは簡単に申し上げれば寺院住職になるための登竜門ですが、僧侶である寺族がさらに研鑽を深めて、仏道に捧げることを決意し、ご門徒様とともに歩むための知識技術素養を身に着けるためのものであります。直前に京都教務所で行われた講習にも参加しましたので、一週間京都に滞在いたしました。

教師検定試験は5科目あり、すべての科目について合格する必要があります。
「声明作法」…本堂の荘厳、各仏具の名称配置、お経や偈文・お文・和讃などの種類特徴、装束の作法・種類・身に着け方、東本願寺の歴史に関する筆記テストと、実際に経本やお道具を用いて声明を行う実技テスト 「法規」…宗教法人法、真宗大谷派宗憲、真宗大谷派規則、各寺院の寺則の四つの法規・規則および、日本国憲法の関連部分について、法規の内容、法規に基づいた寺院の運営事例などに関する筆記テスト 「教化」…親鸞聖人の教説に関する出題のテーマについて、いかにご門徒の皆様にお伝えし、ご門徒の皆様とともに歩む寺院を運営するかに関する事前小論文と小論文に関する口頭試問 「仏教学」…釈尊(お釈迦様)の生誕及び成道なされた経緯から今日に至る、インド・中国・日本における仏教の展開。特に大乗仏教や浄土教が誰によってどのような思想が繰り広げられ、今日に至っているか。試験では7つほどのテーマが出題され、論述で解答します。高校の倫理、世界史の文化の分野が好きだった方には、理解の進む分野だと思われます。 「真宗学」…親鸞聖人のお考えがどのように形成され、どのようにご同朋の皆様に受け入れられていったのかについて、歴史的な流れ動き、お考えのもととなった七高僧の思想とご功績、親鸞聖人やそのお弟子が残された著述の内容について、仏教学と同様に論述で解答をします。

本来ならば大谷大学や同朋大学、大谷短期大学などで学びそのうえで取得する資格を、自力で学んで取得しようとするものですので、容易な試験ではありません。試験会場には様々なご事情を抱えるのであろう、幅広い年齢層の皆さん、大学生と思しきお若い方々、もちろん女性の方もかなりの人数が受検していらっしゃいました。本寺寺族も4月にテキストを大量に取り寄せ、4か月余り時間を見て勉強しましたが、あらためて学ぶことの尊さ、勉強を頑張ることの心地よさなども知ることができたようです。

間もなく秋のお彼岸のご通知、報恩講のご通知を申し上げる予定です。